仙台育英は、宮城県を代表する全国屈指の強豪校で、
特に近年は「全国制覇を狙えるチーム」として注目されており、
横浜高校と並び、優勝候補の筆頭でした。
2022年には東北勢として初の夏の甲子園優勝を果たし、
以降も安定して上位進出を続ける黄金期にあります。
さらに選手はスター選手が揃い、
投手も横川煬大投手を筆頭に、140km/h越えが5人もいます。
まさに穴がなく、確かに優勝候補の筆頭でした。
そんな仙台育英が沖縄尚学にタイブレークの末、
3-5で敗れ、ベスト8に進出することなく、甲子園を去ることになりました。
これがそのときのスコアです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
そこで仙台育英が3回戦でなぜ負けたのでしょうか。
優秀な投手陣はなぜ5点も取られてしまったのでしょうか。
強力打線はなぜ3点に抑えられてしまったのでしょうか。
そこで調べる内容を次にまとめました。
さあみなさんで、いっしょに確認しましょう。
1.得点のポイント
2.【敗因1】優秀な投手陣がなぜ5点も取られてしまったのか
3.【敗因2】強力打線はなぜ3点に抑えられてしまったのか
4.仙台育英はなぜ負けたのか?敗因についてまとめ
1.得点のポイント
① 初回:仙台育英が先制
川尻結大の左前打で1点先制
低めの変化球を拾う技ありの一打
② 中盤:沖縄尚学が逆転
2回・3回に1点ずつ奪い2-1と逆転
比嘉の二塁打などで着実に得点
③ 5回:仙台育英が再逆転
川尻が2点タイムリーで3-2と再逆転
外角直球を右前に弾き返す勝負強さ
④ 7回:沖縄尚学が同点に追いつく
末吉の粘投で流れを呼び込み、3-3の同点
⑤ 延長11回:沖縄尚学が勝ち越し
敵失で1点+宜野座の三塁打で2点追加
合計2点を奪い5-3と突き放す
点を取ったら両者ともすぐに取り返す。
見ごたえのあるゲームでしたね。
2.【敗因1】優秀な投手陣がなぜ5点も取られてしまったのか
優秀な投手陣が5人もいるのに、
なぜ吉川選手を11回まで続投させたのでしょうか。
これが継投であれば、さらに失点も少なかったのではないでしょうか。
そこでなぜ吉川投手を11回まで引っ張ったのか、調査分析してみました。
なぜ吉川投手を11回まで引っ張ったのか
① 【エースとしての信頼と実績】
吉川陽大投手は今大会でも安定した投球を続けており、
10回まで3失点の好投でした。
そして初回から三振を奪うなど、立ち上がりも良好で、
試合を作る力が際立っていました。
② 【他投手との比較と状況判断】
仙台育英には他にも好投手がいるが、延
長タイブレークという特殊な状況では、経験値と精神力が重視されます。
須江監督は「吉川は良く投げてくれた。ナイスピッチングでした」と語っており、
交代のタイミングに後悔はないと明言しています。
③ 【延長戦の流れと采配の一貫性】
10回裏に1死満塁の好機を逃したことで、
流れが沖縄尚学に傾むきました。
11回表の守備で失策が絡み2失点。
これは吉川の投球というより、守備の乱れが要因です。
須江監督の過去の采配スタイルは、
まさしく、「信頼」「試合の流れ」「勝負勘」
なのでしょう。
そして吉川投手の投球については、
ほぼシナリオ通りだったのかもしれません。
ただ誤算だったのは、11回のエラーだけだったのではないでしょうか。
吉川投手の配球が読まれていた
とはいうものの、これだけの大投手である、吉川陽大投手は
沖縄尚学に相当研究されていたと考えられます。
となると配球が読まれていた可能性が大きいです。
次のその根拠を示します。
配球が読まれていた根拠
① 【球種・コースの偏り】
吉川投手は直球とスライダー中心の配球で、
特に右打者には外角低めを多用していたのに対し、
沖縄尚学は外角球を逆方向に打ち返す意識が徹底されていました。
特に宜野座の三塁打は、外角球を狙い澄ましたようなスイングでした。
② 【カウント別の対応力】
沖縄尚学は2ストライク後の粘りが際立っていました 。
変化球の見極めが良く、ボール球を振らない冷静さもありました。
これは「球種の読み」だけでなく、
「カウントごとの配球傾向の把握」があった証拠です。
③ 【延長11回の失点構造】
タイブレークでの先頭打者に対する配球が初球から狙われていました。
失策も絡んだが、打者のスイングが迷いなく、
狙い球に絞っていた印象があります。
これは「配球パターンが読まれていた」可能性を示唆しています。
今後吉川投手が配球を読まれにくくするには、
まずチェンジアップで緩急をつけることと思います。
さらにフォークも取り入れ、この2つの投球で三振率を挙げます。
そしてこの2種でコーナーワークが格段に広くなります。
さらにシンカーを習得することで凡打が築けます。
これだけで、投球の幅が格段に広がり、
読まれにくい投球なるのではにないでしょうか。
3.【敗因2】強力打線はなぜ3点に抑えられてしまったのか
末吉投手の「クロスファイヤー」と投球術の精度
最速150km/hの左腕で、右打者の内角をえぐるクロスファイヤーが
有効に機能し、 特に仙台育英の右打者に対して、
内角高めの直球で詰まらせる場面が多くありました。
スライダーやスクリューボールも交え、
外角への逃げ球と内角への攻め球の緩急が絶妙 で、
169球を投げ切るスタミナと集中力も、終盤の粘りに繋がりました。
つまり、物理的に打ちづらいゾーンに高精度で投げ込める能力が、
打線の爆発力を封じた要因の一つです。
実際仙台育英の各打者は、内角高めの球に、
差し込まれている場面が多かったですよね。
特にクロスファイヤーは仙台育英だから、余計効果的たったのでしょう。
なにせ、仙台育英打線は全員右打者ですから。
今どき強豪校で珍しいですよね。
多分、イチローさんとか松井秀喜さん、そして大谷翔平選手の影響もあって、
リトルリーグの頃から、
右投げ左打ちにする選手が増えているはずですよ。
左打者が増えすぎた現代において、
右打者の育成が“差別化”になるという戦略的な側面もあるのでしょうか。
もしそうだとすると、
右打者が多いこと自体は戦術的な強みになると思いますが、
末吉投手のような“内角を突ける左腕”には不利になることもあるというのが、
この試合の示すところだと思います。
沖縄尚学の仙台育英打線への「研究と対策」
・仙台育英は高田庵冬選手、川尻結大選手、田山纏選手など
長打力と繋がりを持つ打線が特徴です。
・末吉投手は試合前から「自分のピッチングを生かすためにしっかり投げ込んだ」
と語っており、打者の傾向を踏まえた配球が徹底されていました。
・特に、追い込んでからの空振りを取る球種選択が的確で、
仙台育英の「粘りと対応力」を封じ込めました。
初回に失点した後も、冷静に立て直し、
打者の狙い球を外す配球に切り替えていました。
仙台育英は研究されつくすと、現状では相手の対応がしやすいのかもしれません。
全員右打者で、外角〜内角の攻めに対する対応が似通っているからです。
また 長打力のある打者が多く、狙い球が絞られやすいと思います。
そのためもう一回役割分担をしたほうがよいと思います。
1〜2番に「出塁+揺さぶり型」、3〜5番に「長打型」、6〜9番に「小技+機動力型」
を配置することで、打線全体が“読まれにくい構造”になると考えられます。
強打者が多いと、スクイズ・バント・エンドランなどの選択肢が
減ると考えられます。
ですから今回得点機に、決定力不足がでてきてしまいます。
今回のようなタイブレークになることを想定し、
今後は小技と機動力も課題になると考えられます。
4.仙台育英はなぜ負けたのか?敗因についてまとめ
敗因1.『優秀な投手陣がなぜ5点も取られてしまったのか』
について、さらに掘り下げ
①『なぜ吉川投手を11回まで引っ張ったのか』についてですが、
須江監督が吉川投手に全面的な信頼を置いていて、
タイブレークとなった10回までは、
須江監督のシナリオ通りと考えられます。
しかし11回のエラーは想定外だったと考えられます。
②『吉川投手の配球が読まれていた』についてですが、
その可能性は大きいです。
その根拠となる状況が随所にみられました。
敗因2.『強力打線はなぜ3点に抑えられてしまったのか』
についてさらに掘り下げ、
① 『末吉投手の「クロスファイヤー」と投球術の精度 』
によるところは大きいです。
特に仙台育英打線は、全員が右打者なので、
内角をえぐるクロスファイヤーは効果的でした。
②『沖縄尚学の仙台育英打線への「研究と対策」』を十分にしてきた
可能性は大きいです。
その根拠となる状況が随所にみられました。
以上仙台育英はなぜ負けたのか?敗因についてまとめました。
今回の試合は仙台育英の弱点がよくでていた貴重な試合だったと思います。
この機会に対策を十分にして、
さらにレベルアップした最強の仙台育英を
春のセンバツでみせてください。
最後までお付き合い頂き、ありがとうごさいました。
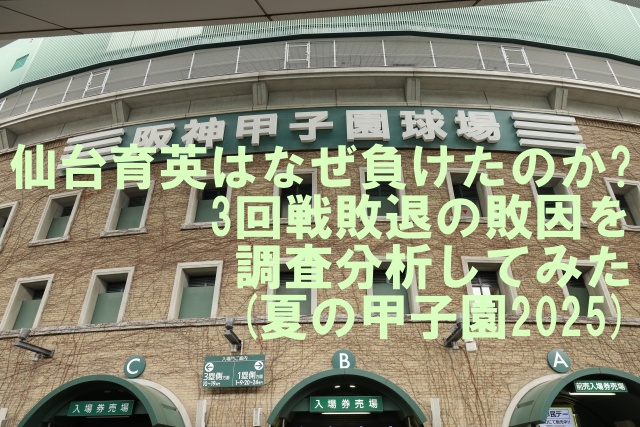


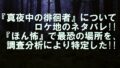
コメント